BASIC【Beginners’ All-purpose Symbolic Instruction Code】
概要
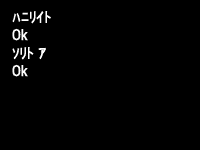
初期のBASIC言語および処理系は、他の本格的なプログラミング言語の多くで必要となるプログラム冒頭の各種の宣言などがほとんど不要で、利用者の必要とする処理を記述するだけでプログラムとして成立する点や、変数宣言を省略していきなり変数を使用してよい点、文字列の扱いが容易で文字列操作の機能が豊富な点など、容易にプログラミングを始められる仕様や特徴が盛り込まれていた。
最初に開発されたのは実行可能ファイルへの変換が必要なコンパイラ型の言語処理系だったが、記述したプログラムを即座に実行してみることができるインタプリタ型の処理系が多く開発され、手軽さからホビー用途や教育用途で特に歓迎された。
一方で、プログラムの構造化のための制御構文など、複雑・大規模なプログラムを整然と記述するための機能が不足し、外部のプログラムを取り込んで利用する機能なども存在しない処理系が多いなど、本格的なソフトウェア開発にはあまり向いていないとされる。
歴史
1964年に米ダートマス大学のジョン・ケメニー(John G. Kemeny)氏、トーマス・カーツ(Thomas E. Kurtz)氏によって考案された。当時の大型コンピュータで大学生などがプログラミングを学ぶのに用いられた。
1970年代後半にパソコン(当時日本ではマイコンと呼んでいた)が発明され普及し始めると、オペレーティングシステム(OS)とソフトウェア開発・実行環境を兼ねた基盤的なソフトウェアとしてBASIC処理系が提供されるようになり、主にホビー用途で主要なプログラミング言語として広まった。
日本ではNECのPC-8001向けの「N-BASIC」、PC-8800シリーズ向けの「N88-BASIC」、富士通のFMシリーズ向けの「F-BASIC」、MSXパソコン向けの「MSX-BASIC」、ファミリーコンピュータでプログラミングができる「ファミリーベーシック」などが提供され、ホビープログラマを中心に人気を博した。
各社が自社の機種やOSに合わせて独自に処理系を開発・提供したため、メーカーごとの仕様の違い(自然言語になぞらえて「方言」と呼ばれる)が大きく、ある機種向けのBASICプログラムは他メーカーの機種ではそのままでは動作しないことが多かった。
米マイクロソフト(Microsoft)社はBASIC言語を元に「QuickBASIC」を、さらにこれを発展させて「Visual Basic」を開発し、自社の主要なソフトウェア開発ツールとして派生言語と共に自社製品の多くに組み込んで提供している。これは記法や一部の機能は初期のBASIC言語を踏襲しているが、大幅な拡張や機能の追加によりほとんど別物となっている。