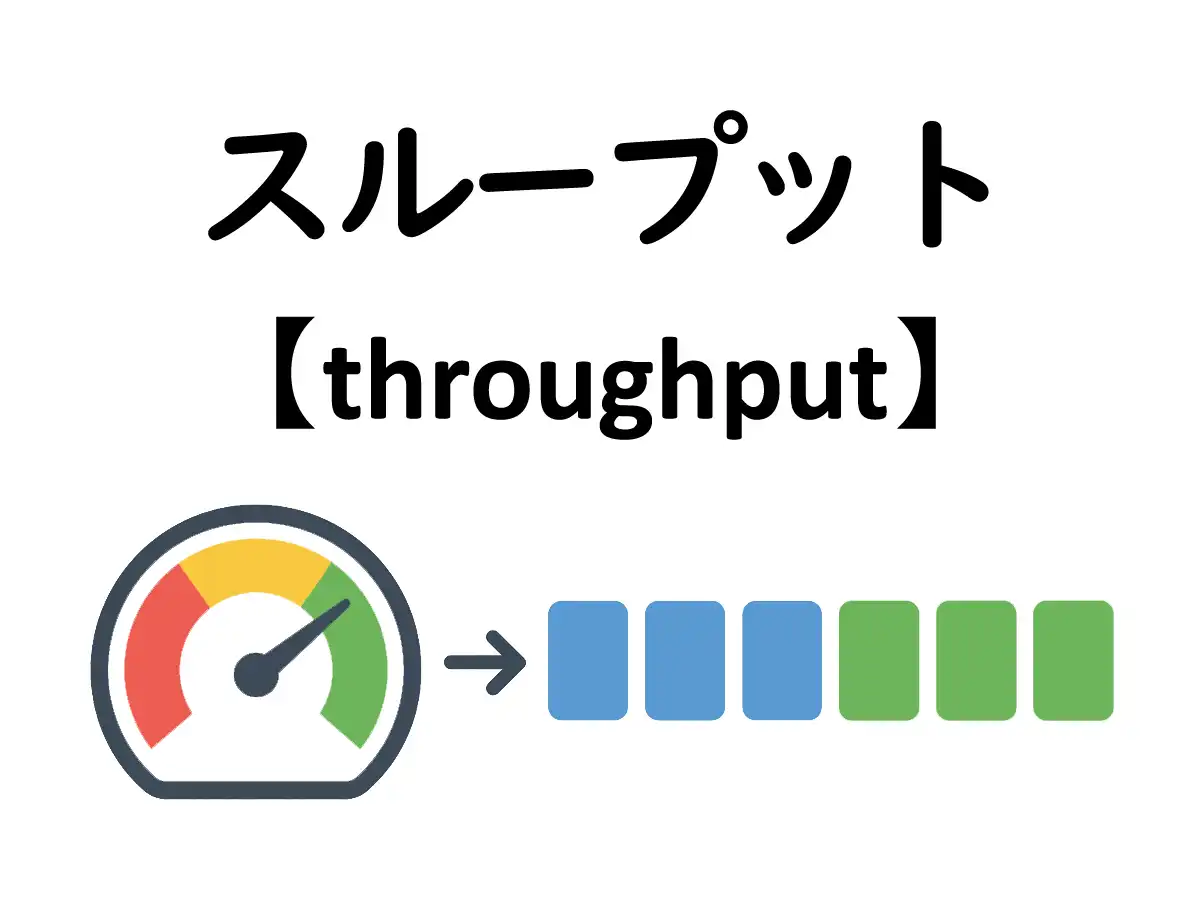スループット【throughput】
概要
連続的に処理や伝送を行ったとき、単位時間あたりにさばくことができる回数やデータ量を表す。設計や仕様、規格などに基づく理論上の上限値のことを「論理スループット」あるいは「最大スループット」と呼び、実際に測定した値を「実効スループット」あるいは「有効スループット」という。
処理のスループット
コンピュータの性能について言う場合は、単位時間あたりに与えられた命令や処理を実行できる回数を表す。CPUやメモリ、ストレージなど装置の構成や性能、処理内容などが複雑に影響しあって決まるため、単一の単純な測定方法や指標はない。
分野や用途、対象の種類などに応じて、企業や業界団体などが試験用のソフトウェア(ベンチマークプログラム)を用意しており、これを実行して実際の処理件数を計測し、基準となる機器を1としたときの相対的な値として表すことが多い。
通信のスループット
通信回線や装置のデータ入出力の性能について言う場合は、伝送路を通じて単位時間あたりに送受信できるデータ量を表す。単位として、1秒あたりに伝送できるビット数である「ビット毎秒」(bps:bits per second)や1秒あたりのバイト数「バイト毎秒」(Bytes/s)、および、これらに大きさを表す接頭辞を付けたもの(Mbps、MBytes/sなど)を用いる。
通信システムやプロトコルなどについて用いる場合は、伝送路自体が全体として運べる理論的なデータ量から、制御データや誤り訂正符号などのオーバーヘッド分を差し引いた、実質的に相手方に伝達されるデータ(ペイロード)の量を表すこともある。
レイテンシとの違い
処理や通信の「速さ」はスループットだけでは決まらず、状況によっては一回ごとにかかる待ち時間や遅延時間である「レイテンシ」(latency)が大きく影響する場合がある。一般に、大量のデータを連続的に扱う場合はスループットが支配的な要因となるが、二者が双方向的に相手からの応答を待って短く何度も繰り返し伝送を行うような状況(通話など)では、レイテンシが支配的となることがある。
例えば、高解像度の映像を伝送できる高スループットの衛星回線でテレビ中継を行っても、出演者が回線越しに会話をすると発言ごとに数秒の「間」が生じることがある。これは、衛星が遠く、一方が電波を送信してから相手方が受信するまでに秒単位の時間がかかることによるレイテンシの影響である。
「スループット」の関連用語
他の用語辞典による「スループット」の解説 (外部サイト)
- ウィキペディア「スループット」
- 日経 xTECH Tech-On!用語「スループット」
- Insider's Computer Dictionary「スループット」
- NTT西日本 ICT用語集「スループット」
- ITトレンド IT用語集「スループット」
- ITパスポート用語辞典「スループット」
- ソフトバンクニュース 1分で分かるキーワード「スループット」
- Programming Place Plus 用語集「スループット」
- TechTerms.com (英語)「Throughput」
- アシストネットナビゲーション 用語集「スループット」
資格試験などの「スループット」の出題履歴
本ページを参照・引用している文書・論文など (外部サイト)
- 総務省 東北総合通信局「沿岸海域における効率的なワイヤレスブロードバンドシステムの技術的条件に関する調査検討会 報告書
」(PDFファイル)にて引用 (2010年3月)