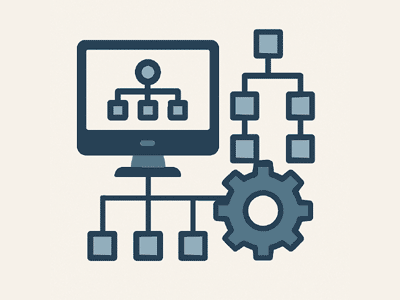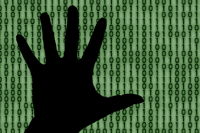BYOD 【Bring Your Own Device】
概要
BYOD(Bring Your Own Device)とは、企業などで従業員が私物の情報端末などを持ち込んで業務で利用すること。私物のスマートフォンを使って出先で社用のメールアドレスのメッセージを確認するといった行為が該当する。解説 私用のスマートフォンやタブレット端末、ノートパソコンなどに業務で利用するソフトウェアの導入や設定を行い、外出先から社内システムにアクセスして業務に必要な情報の閲覧や入力を行うことを意味する。パーティーなどで「飲み物は各自持ち寄り」を意味する “BYOB”(Bring Your Own Booze/Bottle)という英語表現をもじった表現である。
これまで業務で利用する情報機器は会社側が一括で調達して支給するのが一般的だったが、BYODを導入することで企業側は端末購入費や通信費の一部などのコストを削減することができる。従業員側は同種の機器を私物と支給品で「2台持ち」する必要がなくなり、普段から使い慣れた端末で仕事ができる。
かかった経費が従業員の持ち出しになってしまわないように、通信事業者の公私分計サービスで費用を分担したり、通信料金の一部を会社が補助するといった運用が行われることが多い。
会社が支給する端末と異なり、端末の設定や導入するソフトウェアの種類などを会社側が完全にコントロールするのは難しいため、情報漏洩やマルウェア感染などへの対策や、紛失・盗難時の対応などが複雑になることが多い。
また、業務中に利用できる機能やアクセスできるサイトを制限するといった対応も難しくなる。本来私用の端末であるため、通信履歴や保存したデータなどをどこまで会社側が取得・把握するかといったプライバシーとの両立の問題もある。
機器に限らず、個人で購入したソフトウェア製品や個人契約のネットサービスなど、個人に属する様々なIT資産を業務に持ち込んで使用することを総称して「BYOX」(Bring Your Own X)あるいは「BYO」という。
COPE (Corporate Owned, Personally Enabled)
企業などが従業員に支給した情報端末などで、一定の条件や制限のもと私的な利用を許可することを「COPE」(Corporate Owned, Personally Enabled)という。
BYODとちょうど逆の方式で、機器は組織に属するが、これを所持・利用する従業員の個人的な使用を一定の範囲で認める。端末について何種類かの選択肢を提示し、従業員が希望する製品を選べる方式は「CYOD」(Choose Your Own Device)という。
企業にとっては端末の購入代金などはかさむが、端末の種類を揃えることで導入・運用のコストを抑えたり、共通のソフトウェア運用やセキュリティ設定によりリスクを軽減することができる。従業員にとっては、私的利用に制限はあるものの、自己負担なく一台の端末を仕事とプライベートの両方で利用することができる。