イーサネットヘッダ【Ethernet header】Ethernetヘッダ
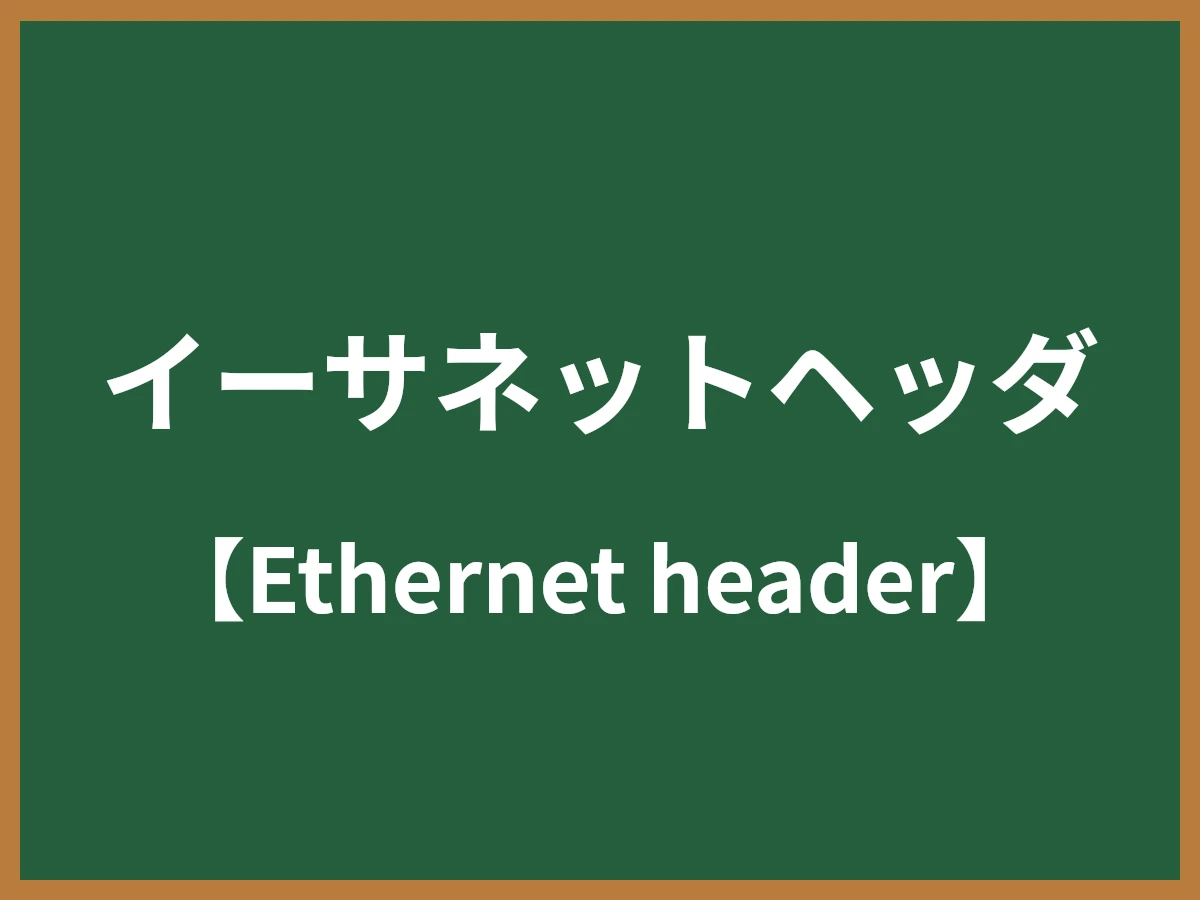
イーサネットでは送りたいデータ(ペイロード)を決まった長さ(46~1500バイト)ごとに分割し、前後に制御情報を付加した「フレーム」(frame)を一単位として、連続した信号で送受信する。上位層のプロトコル(通信規約)が送受信するデータはペイロードの中に格納されており、プロトコル階層に従って入れ子構造となって運ばれる。
フレームは先頭部分が宛先などの制御情報が格納された固定長の領域となっており、これをヘッダという。フレーム形式の仕様はいくつかあるが、最も一般的なEthernet II(DIXイーサネット)形式の場合、先頭から順に、宛先MACアドレス(6バイト)、送信元MACアドレス(6バイト)、「EtherType」と呼ばれる送信データの種類(2バイト)となっている。
VLANを利用する場合には、送信元とEtherTypeの間に、IEEE 802.1Q規格で定められたVLANの識別番号(タグ)を記載するための4バイトの領域が挿入される。EtherTypeの領域はIEEE 802.3規格ではバイト単位のペイロード長を表すと規定されており、これに従って長さを記載するシステムもある。ペイロードは1500バイトまでと規定されるため、1500以下なら長さ、1536以上ならEtherTypeと解釈される。1501~1535の値は通常は使用しない。
なお、データリンク層レベルのイーサネットフレームは宛先MACアドレスから始まるが、物理層(電気信号)のレベルでは、受信側にフレームの開始を知らせるため、ヘッダよりも前に決まったビットパターンのプリアンブル(7バイト)とSFD(Start Frame Delimiter/1バイト)の8バイトが付加される。
(2023.6.16更新)