読み方 : ますきごう
枡記号【〼】
概要
枡記号とは、記号の文字の一つで、正方形の中に右上から左下に向かって斜線を引いた「〼」のこと。丁寧語の文末「~ます」の置き換えとして、かつてよく用いられていた。
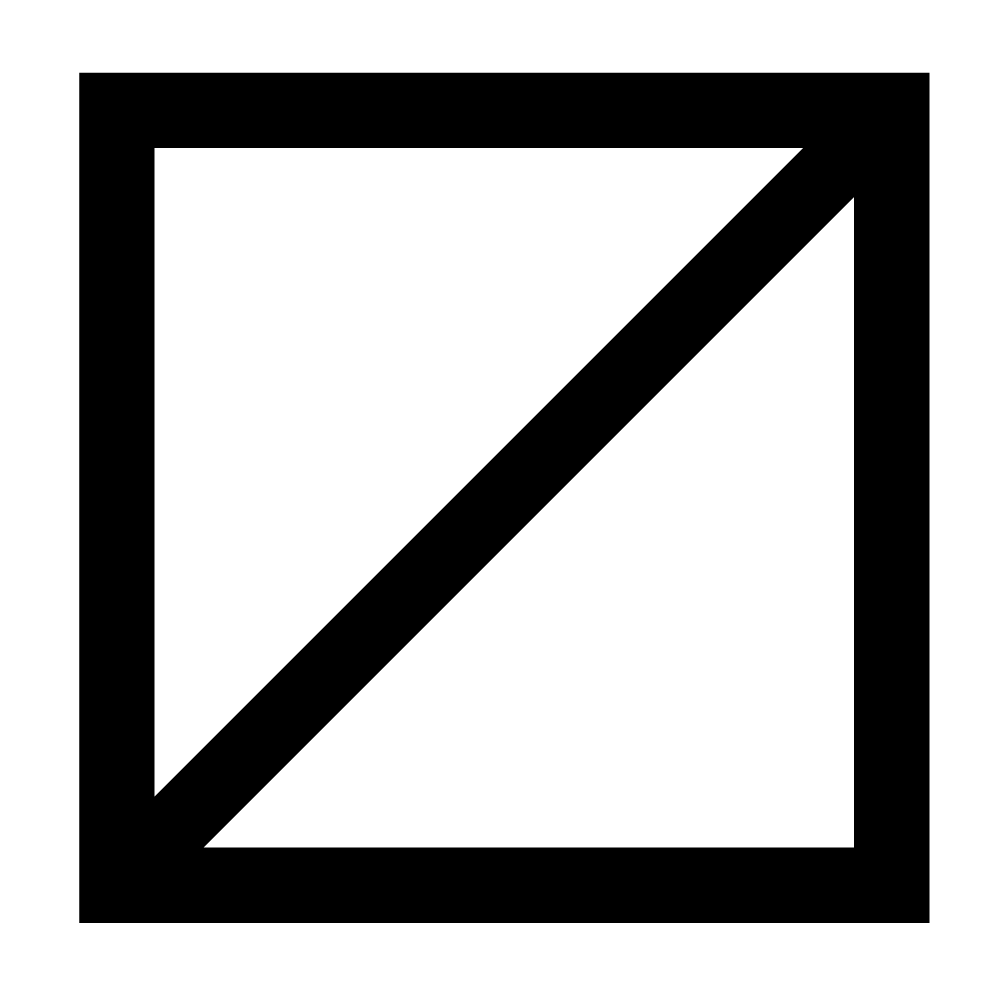
日本語の記号の一つで、古くから容積のはかりとして使われてきた枡を表している。上部の対角線に金属製の棒をわたした「弦掛枡」を上から見た図を模式化したものが由来とされる。
昭和の頃までは、店先などで「ラムネ冷えて〼」のように助動詞「~ます」の置き換えとして用いる例が見られた。江戸時代から見られる用例で、かつては「益々」を「〼〼」とするなど、様々な用例があったとされる。現代ではレトロ風の演出などを除いて、ほとんど見かけることはない。
コンピュータ上の文字としては、2000年にJIS X 0213として日本語文字コードに収録され、以降に提供されたシステムで利用できるようになっている。日本語入力システム(IME)で「ます」から変換することで入力できるが、登録がない場合はJIS X 0213の区点番号(1面2区23点)やUnicodeのコードポイント(303C)で呼び出せる場合がある。
国際的な文字コード標準のUnicodeにも「MASU MARK」の名称で12348番(U+303C)として収録されており、広く利用できるようになっている。Unicodeでは似た形の記号として「⍁」(U+2341/APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD SLASH)や「⧄」(U+29C4/SQUARED RISING DIAGONAL SLASH)などもある。
(2025.8.28更新)