読み方 : かぎかっこ
鉤括弧【corner bracket】かぎかっこ
概要
鉤括弧とは、日本語の表記に用いられる記号(約物)の一つで、会話や引用などを表す 「 」 のこと。
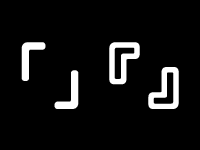
文章中で登場人物の会話(台詞)や、他の文章からの引用箇所、作品名や固有名詞などを表すために用いられる。また、『彼の「正義」とは結局のところ、』といったように、地の文と区別して他者の主張であることを明確にしたい場合にも用いられる。内部には原則として句点(。)は打たない。
日本語の文章では、地の文を構成する語や句について、単に強調や(同じ文字種が続く場合の)分かち書きのために鉤括弧で括ることもあるが、英語などの引用符(クォーテーションマーク)にこのような用法はないため、日本人が英文で強調のために引用符で括ったものが他者の主張(著者は認めていないか疑っているという含意がある)のように受け取られ真意が伝わらない場合がある。
コンピュータ上の文字としては日本語文字コード標準に収録されており、古くから使われている、いわゆる半角カタカナの一部である半角鉤括弧 「 」 と、全角鉤括弧 「 」 がある。キーボードでは日本語入力モードで『{ 「 [ ゜』キーを押すと開き括弧、『} 」 ] む』キーを押すと閉じ括弧を入力できる。
内部が白くなっている 『 』 は「二重鉤括弧」と呼ばれ、引用や台詞の中に別の引用や台詞が含まれる場合に内側の鉤括弧をこれで置き換えたり、複数の作品を集めた作品集の題名(音楽のアルバムCDなど)や、内部が複数の作品や記事に分かれている出版物(単行本や新聞、雑誌など)の題名などの表記に用いられることがある。
(2023.11.15更新)