読み方 : とっきょけん
特許権【patent right】パテント
概要
特許権とは、知的財産権の一種で、自然法則を応用した発明を考案者が一定期間、独占的に使用する権利。機械などの物体のほか、方法や手段、仕組み、コンピュータプログラムなどにも認められる。
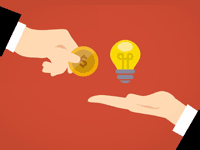
日本では特許法によって保護され、特許庁に出願して登録されると権利が発効する。発明を審査・登録して出願者に権利を付与する行政手続きを「特許」というが、一般には特許登録された発明(特許発明)のことを指して特許ということが多い。
特許権の対象となる発明とは、自然科学の法則を応用して新たに考案された物や方法、物を生産する手段などで、特許発明として登録されるには新規性や進歩性、産業への応用可能性がなければならない。
出願された内容がすでに公知の場合や、科学的に実在を確認できない原理や存在に基いている場合、自然科学の法則を利用していない場合、既存の技術よりあらゆる面で劣っている場合、産業における有用性が見込めない場合、公序良俗や法律に反する目的や手段を含む場合などは、審査により却下される。
特許発明の出願者には独占的な使用権が認められ、発明を許諾なく使用した者に対し、使用の差し止めや損害賠償を請求することができる。特許権の有効期間は日本の現在の制度では出願から20年間で、原則として延長はできないが、薬品などごく一部の分野に限って5年間の延長が認められる。登録中は毎年特許庁に特許料を収めなければならず、これを怠ると20年を待たずに特許権は消滅する。
特許発明の内容は特許庁によって公開され、誰でもその詳細を知ることができる。また、特許権は商標権のように任意の期間延長することはできず、存続期間が終了すると誰でも自由にその発明を利用できるようになる。
このため、自社の優位を少しでも長く維持したい企業や、知的財産権の保護体制が未整備な国への技術流出を恐れる企業では、自社独自の技術などをあえて特許出願せず、秘密を厳重に管理して守ろうとする場合もある。
(2021.4.22更新)
「特許権」の関連用語
他の用語辞典による「特許権」の解説 (外部サイト)
資格試験などの「特許権」の出題履歴
▼ ITパスポート試験
【令4 問1】 著作権及び特許権に関する記述 a〜c のうち、適切なものだけを全て挙げたものはどれか。a 偶然二つの同じようなものが生み出された場合、発明に伴う特許権は両方に認められるが、著作権は一方の著作者にだけ認められる。
【令4 問6】 自社開発した技術の特許化に関する記述 a〜c のうち、直接的に得られることが期待できる効果として、適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
【平30春 問16】 特許法における特許権の存続期間は、出願日から何年か。ここで、存続期間の延長登録をしないものとする。
【平28秋 問21】 特許権に関して、次の記述中の a、b に入れる字句の適切な組合せはどれか。特許権とは [ a ] を独占的・排他的に利用できる権利であり、我が国の法律では [ b ] に与えられる権利である。
【平28春 問23】 知的財産権のうち、全てが産業財産権に該当するものの組合せはどれか。
【平26秋 問27】 ビジネスモデル特許として、特許法に基づく特許権が認められる対象となるものはどれか。
【平23秋 問20】 コンピュータソフトウェアを使った新しいビジネスの方法に関して取得できる知的財産権として、適切なものはどれか。
▼ 基本情報技術者試験
【平23修7 問77】 特許権を説明したものはどれか。
【平21春 問79】 特許権を説明したものはどれか。