入出力インターフェース【I/Oインターフェース】Input/Output interface
概要
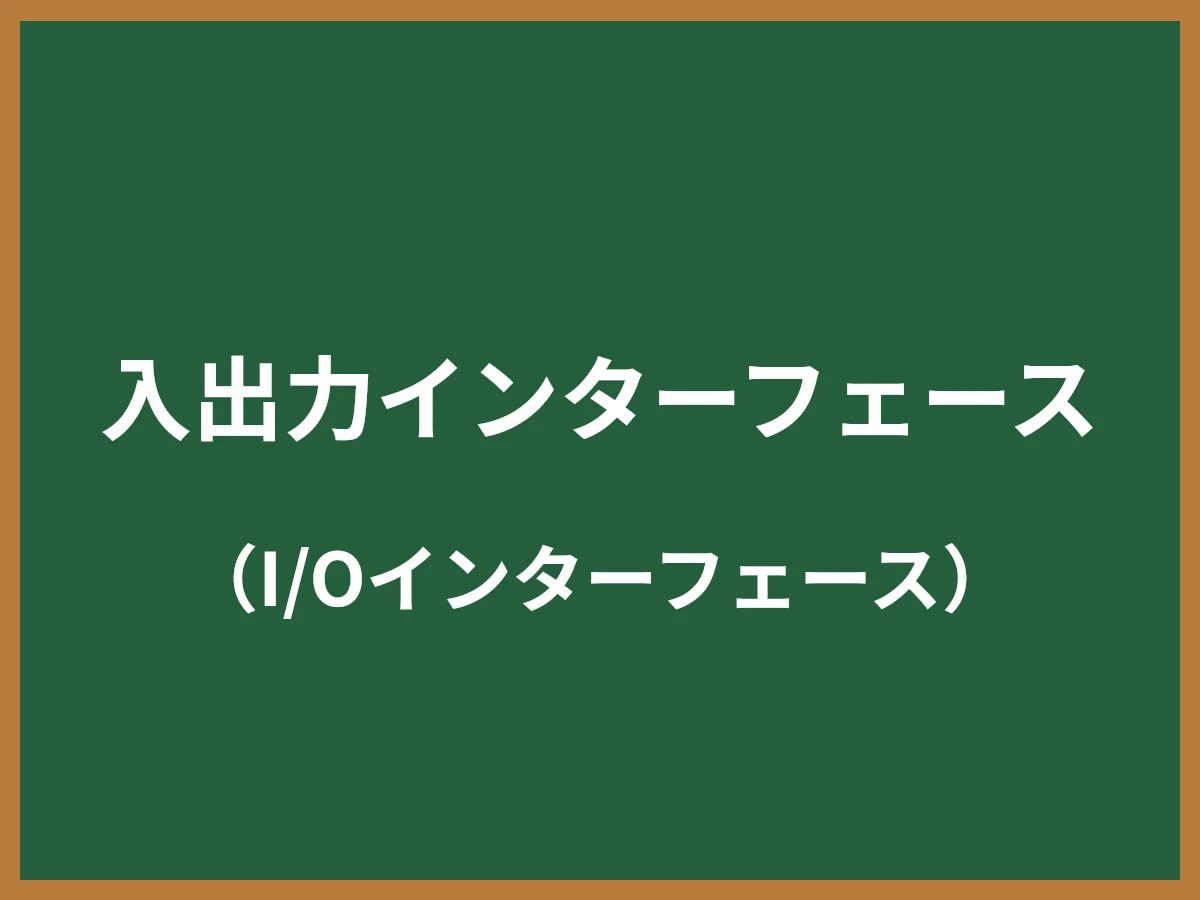
コンピュータの中枢部である主基板(マザーボード)およびCPU、チップセットなどから、端子やケーブル、無線などを介して別の機器を接続し、データや制御情報を送受信する仕組みを指す。様々な種類の機器を接続できる汎用的な規格と、特定の機器との通信に特化した規格がある。
現代の一般的なパソコン製品などの場合、キーボードやマウス、プリンタなどの装置は汎用のUSB(Universal Serial Bus)を、ディスプレイとの接続には専用の規格(DVI、DisplayPort、HDMIなど)を用いることが多い。マイクやスピーカー、イヤフォンなどの音響装置は、一般的なオーディオ機器と共通のステレオミニプラグがよく用いられる。
ハードディスクやSSD、光学ドライブなどストレージ装置の接続にはSATA(Serial ATA)やThunderbolt、NVMe、M.2、IEEE 1394(FireWire)、Fibre Channelなどが、拡張カードの接続にはPCI Expressが広く普及している。スマートフォンなどの携帯機器ではBluetoothやNFCなど電波による無線通信で機器間を接続するインターフェースも利用される。
複数の信号線で同時に信号を伝送する方式を「パラレルインターフェース」(parallel interface)、一本の信号線で順番に信号を伝送する方式を「シリアルインターフェース」(serial interface)という。かつては高速なデータ伝送を要する用途によくパラレル方式が用いられた(SCSIやパラレルポートなど)が、技術的な限界に達し、現在は高速な用途でもシリアル方式が主流(USBやSATAなど)となっている。
多くの接続仕様は公的な標準化団体や業界団体によって標準化されており、メーカーをまたいで接続することができるが、米アップル(Apple)社の製品に採用されているLightningケーブル/ポートなど、メーカー独自の接続仕様も存在する。
インターフェースは技術の進歩に合わせて時代とともに移り変わり、かつて広く普及していたが現在ではあまり用いられない(あるいは特定分野・業界でしか見られない)ものもある。PS/2ポート、シリアルポート(RS-232Cなど)、パラレルポート(セントロニクス仕様/IEEE 1284)、IDE/ATA、SCSI、PCカード、IrDA、アナログRGB(VGA端子)、ISAバス、PCIバスなどである。