RISC【Reduced Instruction Set Computer】縮小命令セットコンピュータ
概要
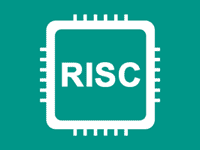
命令語の種類や内容を規定する命令セットアーキテクチャ(ISA:Instruction Set Architecture)の分類の一つで、単純な機能を持つ少数の命令語のみを実装し、すべての命令の語長と実行時間(クロック数)を同一に揃えている。これにより、パイプライン処理で待ち時間が生じなくなるため、どの命令も1クロックで実行することができる。
各命令の実行回路は半導体素子を物理的に結線した論理回路(ワイヤードロジック)で実装されるため、命令をより小さな動作単位であるマイクロコードへ変換・分解する必要がなく、少ないクロック数で高速に実行することができる。回路規模も小さく、チップのサイズや消費電力も抑えることができる。
RISC方式は1970年代後半に、複雑化する一方の命令セットやプロセッサ設計に対するアンチテーゼとして考案された。これ以降、従来型の不揃いで高機能な命令セットを用いる設計様式を「CISC」(Complex Instruction Set Computer:複合命令セットコンピュータ)と呼んで区別している。
主な製品
代表的なプロセッサ製品として、米IBM社のPOWERシリーズ(および小型機器向けのPowerPCシリーズ)、米ミップス・テクノロジーズ(MIPS Technologies)社のMIPSシリーズ、旧サン・マイクロシステムズ(Sun Microsystems)社(現Oracle社)のSPARCシリーズ、ルネサステクノロジのSuperHシリーズ(元は日立製作所の製品)などがある。
最も成功していると言われるのは英アーム(ARM)社のARMアーキテクチャで、主にスマートフォンなど携帯情報機器に広く採用されている。同社は命令セットなどを他社にライセンス供与するのみで製品の製造・販売は行っておらず、具体的なプロセッサ製品は提携各社から提供されている。
パソコン向けではCISC型の米インテル(Intel)社x86シリーズや互換製品が圧倒的に強く、RISC型プロセッサはそれ以外の市場、特にUNIX系ワークステーション/サーバや組み込み機器、家庭用ゲーム機、デジタル家電、スマートフォンやタブレット端末などで採用されることが多い。
「RISC」の関連用語
他の用語辞典による「RISC」の解説 (外部サイト)
- ウィキペディア「RISC」
- 日経 xTECH IT基本用語辞典「RISC」
- Insider's Computer Dictionary「RISC」
- EDN Japan Q&Aで学ぶマイコン講座「RISC」
- くみこみックス「RISC」
- TechTerms.com (英語)「RISC」
- PC.net Computer Glossary (英語)「RISC」
- WhatIs.com (英語)「RISC」
- Techopedia (英語)「Reduced Instruction Set Computer」
- Gartner Information Technology Glossary (英語)「RISC」