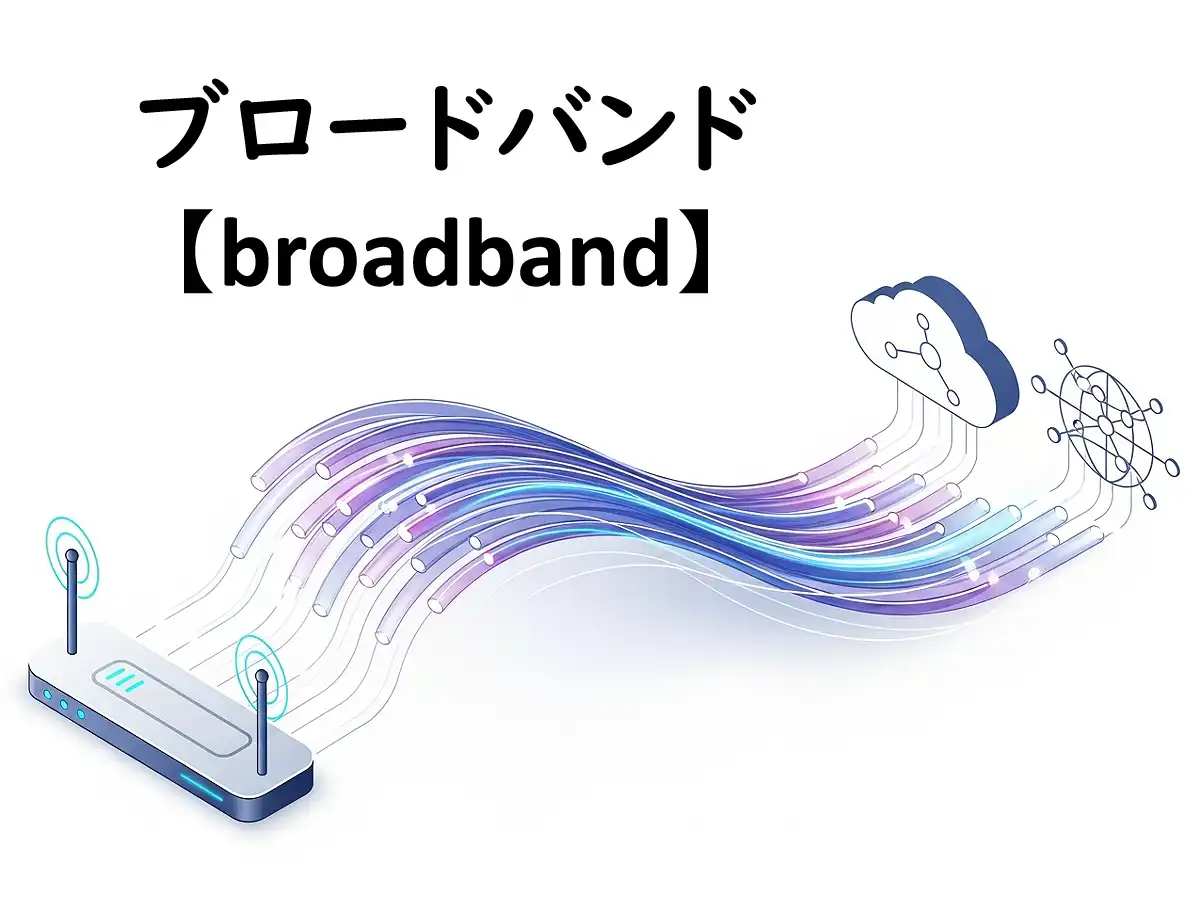ブロードバンド【broadband】広帯域
概要
インターネットが一般に普及し始めた1990年代末、それまでのアナログ電話回線(~56kbps)、ISDN(~128kbps)、第2世代携帯電話(~9600bps)等の低速な通信回線と区別して、当時普及し始めたばかりの、より高速な通信環境を指す用語として広まった。
日本では、おおむね500kbps(キロビット毎秒)程度か、それ以上の通信速度を持つ方式を指すことが多い。ADSLなどのxDSLや、ケーブルインターネット、光ファイバー回線(FTTH)、Wi-Fi、3G(W-CDMA/CDMA2000)以降のモバイルデータ通信などが該当する。
ブロードバンド通信の特徴
ブロードバンド回線は旧来の方式に比べ通信速度が速いというだけでなく、それまでのアナログ電話回線のように明示的に回線の接続や切断の操作を行わなくても常時接続していつでもインターネットを利用できる点や、様々な通信サービスを多重化して同時に利用できるといった特徴もある。
これを活用して、音声をデータ化してパケット通信で伝送するIP電話(ケーブルテレフォニ、光IP電話、VoLTE等)や、データ通信に放送信号を重畳して地上波や衛星のテレビ放送を視聴できるサービスが提供されている。インターネット接続に限らず、通話や放送などを統合した総合情報インフラとして普及している。
「ブロードバンド」の死語化
2010年代になると、日本を含む先進国ではダイヤルアップ接続などの低速の通信方式がほぼ姿を消し、高速・常時接続のデータ通信に適した回線が一般的となり、高速回線を区別する必要性が薄くなった。これに伴い、「ブロードバンド」という用語は以前ほど使われなくなり、単にインターネット接続サービスを指すようになった。
また、平均的な通信速度の向上に伴って、米連邦通信委員会(FCC)などでは1.5Mbpsといった初期のADSL方式などを除外した、より高速な回線のみを指す定義を用いるようになっている。OECD(経済協力開発機構)の国際的な統計では、下り(通信事業者→加入者方向の通信)で256kbps以上という基準を採用している。
「ブロードバンド」の関連用語
他の用語辞典による「ブロードバンド」の解説 (外部サイト)
- ウィキペディア「ブロードバンド回線」
- 総務省 国民のためのサイバーセキュリティサイト 用語集「ブロードバンド」
- 日経 xTECH ITレポート(キーワード3分間講座)「ブロードバンド」
- 日経 xTECH IT基本用語辞典「ブロードバンド」
- 三省堂 10分でわかるカタカナ語「ブロードバンド」
- @IT ネットワーク用語辞典「ブロードバンド」
- 日本インタラクティブ広告協会 インターネット広告基礎用語集「ブロードバンド」
- Insider's Computer Dictionary「ブロードバンド」
- NTT西日本 ICT用語集「ブロードバンド」
- リセマム ひとことで言うと?教育ICT用語「ブロードバンド」