アナログ【analog】
概要
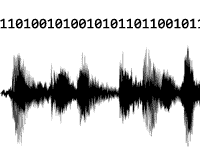
対義語は「デジタル」(digital)で、情報を離散的な数値に変換し、段階的な物理量として表現する。アナログで情報を扱う利点として、デジタル化では避けられない離散化に伴なう本来の信号からのズレ(量子化誤差)が生じないという点があり、情報の発生時点では正確に表現して記録することができる。
一方、保存や伝送、再生、複製に際して劣化やノイズによる影響を受けやすく、変化した情報は復元することができないため、伝送・複製を繰り返したり長年に渡って保存すると内容が失われたり変質してしまう難点がある。
かつて音楽の販売に用いられたレコード盤は、樹脂表面に刻まれた溝の凹凸の変化が音声信号の変化に直接対応付けられたアナログ記録方式だったが、コンパクトディスク(CD)では音声信号をサンプリング(標本化)して離散的な数値の列に変換し、これを表面の溝の凹凸にデジタル信号として記録している。
機器などの内部的にはデジタル処理が行われていても、人間には連続的に感じられる多段階の値で量を識別するような方式を便宜上アナログと呼ぶ場合がある。例えば、ゲーム機のコントローラの種類の一つで、方向の指示を多段階に滑らかに変化させられるものをアナログコントローラという。
1990年代頃までは、コンピュータなどによる情報のデジタル処理は限られた用途にのみ用いられてきたが、半導体チップやデジタル機器の性能向上や低価格化により、現代では身近な情報の多くがデジタル方式で保存、加工、伝送されるようになってきている。
比喩や誤用
コンピュータやデジタル方式の情報機器、通信サービスなどが普及するに連れ、旧来の機器や仕組み、考え方などを比喩的にアナログと称するようになった。
そのような用例の多くは情報の表現形式のデジタル・アナログとは無関係で、単に「コンピュータやインターネットによらない」という意味だったり、さらには「電気機械を使わない」ことを表していたりする。
中には本来の語義では誤用と思われる用例もある。例えば、ビデオゲームと対比してカードゲームやボードゲームを「アナログゲーム」と呼んだり、パソコンや電卓と対比してそろばんを「アナログな計算方法」と評することがあるが、これらが扱う情報は離散的な数値であり、電気機械を使っていないだけで情報の取り扱い方自体はデジタル的である。
「アナログ」の関連用語
他の用語辞典による「アナログ」の解説 (外部サイト)
- ウィキペディア「アナログ」
- NTT東日本 BizDrive 用語解説「アナログ」
- ボクシルマガジン「アナログ」
- Programming Place Plus 用語集「アナログ」
- TechTerms.com (英語)「Analog」
- PC.net Computer Glossary (英語)「Analog」
- Techopedia (英語)「Analog」
- PC Magazine (英語)「analog」