スプリットブレインシンドローム【split-brain syndrome】
概要
スプリットブレインシンドロームとは、機器の障害に備え同等の機器を待機させるクラスタシステムなどで、同時に複数の系統が稼働状態になってしまい、外部に正しくサービスを提供できなくなってしまうこと。
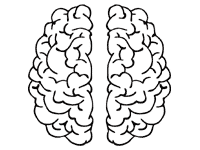
高可用性クラスタ(HAクラスタ)などの冗長化方式では、通常時に稼働する稼働系と、稼働系の停止を検知すると瞬時にサービス提供を肩代わりする待機系から成る「アクティブ/スタンバイ構成」となっている。
システムは一系統で運用する構成されており、待機系は稼働系が停止した場合にのみ稼働するようになっているが、両者の通信が寸断されるなどして、実際には稼働系は動作しているのに待機系からは稼働系が停止したように見え、誤って待機系も起動してしまうことがある。
この状態がスプリットブレインシンドロームで、同時に両系統が稼働状態となってしまうため、外部からはどちらにアクセスしてよいか分からなくなってしまう。ストレージなど共有資源がある場合には、両者で同時に読み書きが発生するなど競合状態となり、データが破壊されたり処理内容に矛盾を生じたりする。
ノード間の通信が絶たれてしまうと互いに相手方の状況を知ることができないため完全にスプリットブレインシンドロームを防止することは難しいが、クラスタソフトウェアなどの中にはストレージシステムを介して生存ノードを決定する仕組みを持つものなどもある。
(2021.12.26更新)