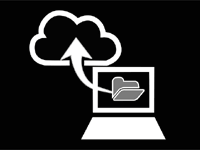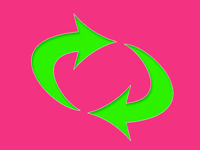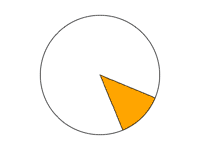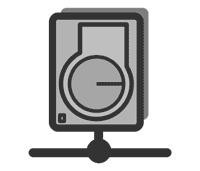読み方 : レイドシックス
RAID 6 【Redundant Arrays of Inexpensive Disks 6】
概要
RAID 6(Redundant Arrays of Inexpensive Disks 6)とは、複数の外部記憶装置(ハードディスクなど)をまとめて管理するRAID技術の方式の一つで、データから誤り訂正符号を2つ生成し、データとともに分散して書き込む方式。解説 RAID(Redundant Arrays of Inexpensive Disks)は複数のストレージ装置を一体的に運用し、広大な単一の記憶領域を作り出したり耐障害性を高める技術で、「RAID 0」から「RAID 6」までの7種類が定義されている。
RAID 6はそのうちの一つで、最低4台の記憶装置を用意し、データを各装置に均等に分散して並列に記録する。その際、一定の長さのデータごとに「パリティ符号」(parity code)と呼ばれる誤り訂正符号を2種類算出し、データとともに分散して記録する。
これにより、いずれか1台、あるいは2台が同時に故障しても、残りの装置に記録されたデータとパリティから元のデータを復元することができる。同時に3台以上が破損すると記録されたデータは失われる。パリティの分だけ容量が圧迫されるため、実質の記憶容量は4台の構成で元の容量の50%(2台分)、5台の構成で60%(3台分)となる。
RAID 5のパリティを2つに増やした方式と考えることができ、対障害性が向上しているが、パリティが増えた分だけ書き込み時の処理が増えて性能が落ちるほか、記憶容量の利用効率も下がる。故障した装置の交換・復旧を待つ間にもう一台が故障するという事象が起きる確率は低く、RAID 5の応用で対応可能なケースが大半なため、あまり普及していない。
(2024.1.28更新)