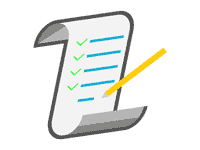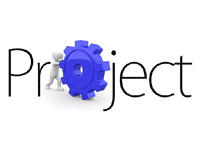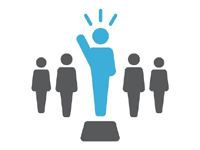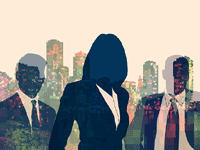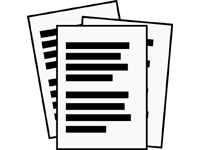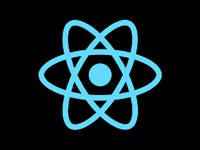自社開発 【in-house development】
概要
自社開発(in-house development)とは、自社で企画した情報システムやソフトウェアなどを、外部に委託せず自社で開発すること。他社が企画したシステムの開発を請け負う「受託開発」の対義語。企画、設計、開発までの全工程を一貫して自社内で行う事業を指す。業務の一部を外部に委託することはあるが、部分的、補助的なものに限られる。自社の製品として外部にパッケージ販売したり、自社ネットサービスを構成するシステムの開発で行われることが多い。
一方、他社が必要とするソフトウェアやシステムの開発業務を受託して納品する事業を受託開発という。日本では伝統的に大企業や官公庁が社内で使用するシステムの開発を専門の事業者に委託することが多く、自社で使用するシステムを自社開発する例はITが本業である企業以外では稀であるとされる。
開発委託との違い
企画側から見て、開発業務を外部に委託する場合と比較すると、委託先などの都合や能力に影響されずにプロセスやツール、品質、コスト、スケジュールなどをコントロールできる。企画、開発、保守、販売(製品の場合)あるいは運用(社内システムの場合)など、各部門・工程間の調整や連携も自社内で完結する。
ただし、システム開発に関するすべての機能・人材を自社内で抱え続けなければならないため、非IT企業が社内システムのみを対象に自社開発を行うことは現実的には難しく、IT関連企業が自社製品・サービスの開発を社内で行い、開発業務が少ない時期は他社のシステム開発を受託するという形態が多い。
受託開発との違い
一方、開発側から見て、他社が企画したシステムの開発を受託する場合と比較すると、開発業務それ自体からは対価を得ることができず、収益の大きさは導入したシステムの効果による利益の増大(自社システムの場合)、あるいは、製品やサービスの市場での成功に依存する。
しかし、開発案件の市況や発注元との力関係といった社外の都合、要因に左右されることが少なく、自社ですべて意思決定できるため、事業としての独立性、自律性は高い。IT関連のベンチャー企業などが受託開発で当面の事業コストを賄いつつ、独自製品の自社開発を目指す事例はよく見られる。