読み方 : こうせいきょうそうそがいせい
公正競争阻害性
概要
公正競争阻害性とは、事業者の行為が、市場における自由かつ公正な競争を阻害する恐れがある状態を表す性質。独占禁止法において、事業者の行為が違法となるか判断する際の重要な基準として用いられる。
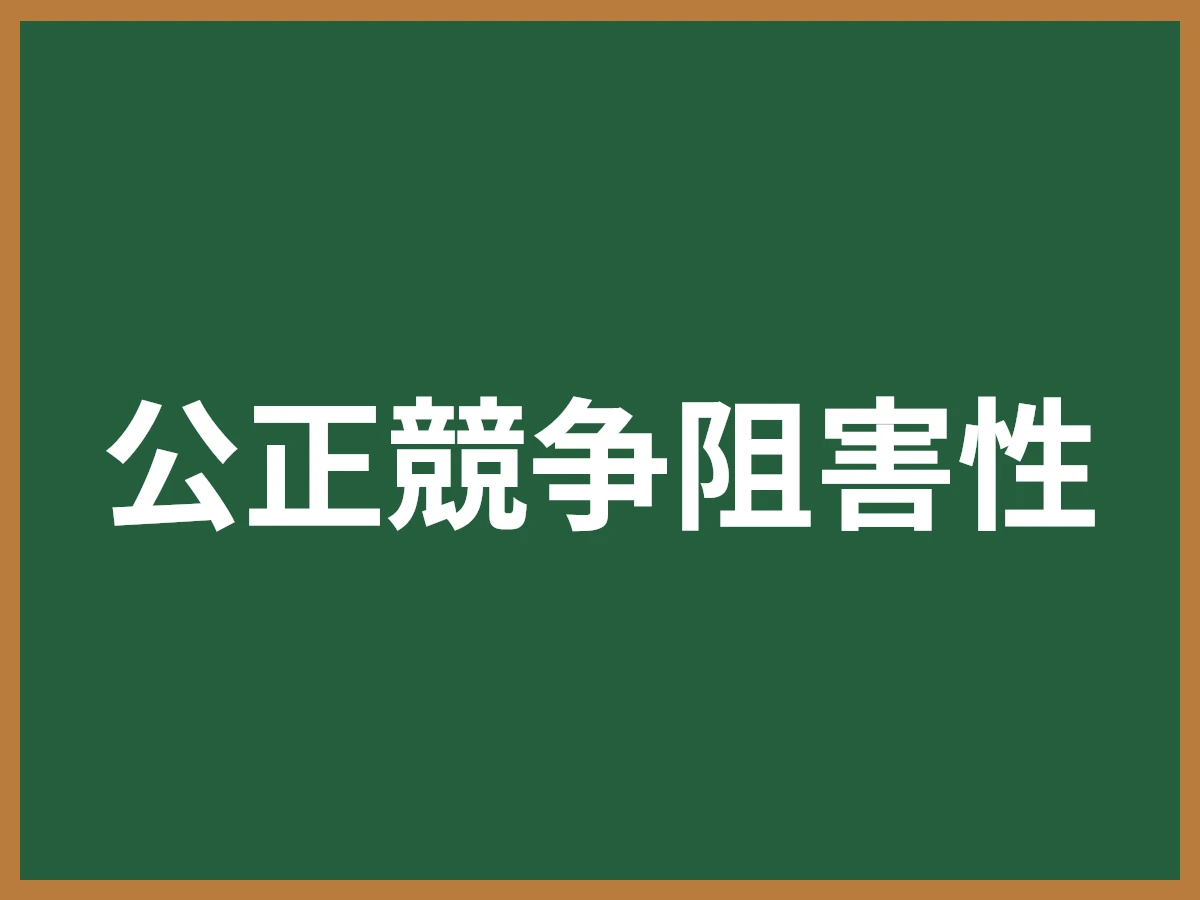
独占禁止法は、市場の自由な競争を確保することを目的としている。その中で不公正な取引方法は、競争の基盤を損ない長期的・間接的に競争を阻害する行為として規制されている。事業者の行為がこれに該当するかを検討する際に問題となるのが公正競争阻害性である。
公正な競争が阻害される状況は、主に次の三つの類型に整理される。一つ目は「自由な競争の侵害」で、取引先に競合他社と取引しないよう強制したり、不当廉売で競合他社を市場から排除するなど、自由な競争が成立しなくなる状況を生じさせる行為である。
二つ目は「競争手段の不公正」で、欺瞞的な取引、不当な利益供与による顧客獲得、抱き合わせ販売など、製品や事業と無関係な競争手段を用いて市場を歪める行為である。三つ目は「自由競争基盤の侵害」で、優越的な地位を濫用して立場の弱い取引先(下請事業者、販売店など)に対して不利な取引条件を強要するなど、事業者の自由意志に基づく取引を阻害する行為である。
公正競争阻害性の有無を判断する際には、市場構造、事業者の市場シェア、取引先への影響、競争事業者の排除の程度、参入障壁の形成状況など、多くの要素が総合的に考慮される。阻害性が認められ、独占禁止法に違反する行為が認定された場合には、公正取引委員会によって当該事業者に排除措置命令が発令される。
(2025.11.27更新)