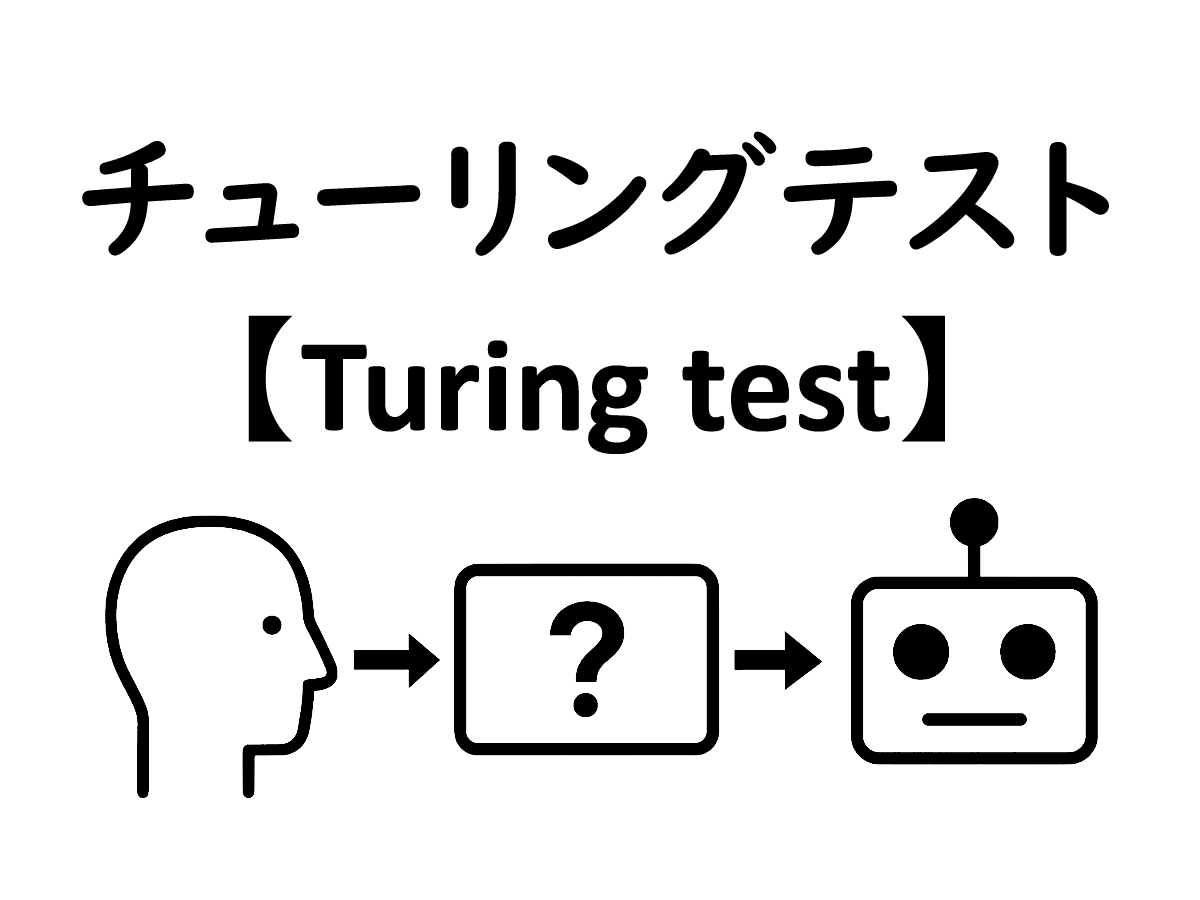チューリングテスト【Turing test】
概要
1950年にイギリスの数学者アラン・チューリングが提案した手法で、人間の知性の定義や詳細な仕組みが分からなくても、人間とやり取りして機械であると見抜けなければ、その機械は内実はどうあれ人間と同程度には知的に振る舞っている証明になっていることを示している。
テストの形式
チューリングはいくつかの方式を提唱しているが、最初に提案したのは次のテストである。人間の試験官が別室の男性と女性に何度か質問し、どちらが男性でどちらが女性かを当てる。姿を見たり声を聞くことはできず、文字(紙のメモ)のみでやり取りする。
男性は女性を装い、どちらが女性か見抜けないように演技する。この男性側を人間(実際の男性)と機械が交代しながら何度も繰り返し、人間と機械が同程度の頻度で試験官を「騙す」ことに成功すれば、人間と同じように振る舞う機械とみなして構わないというものである。
批判と合格事例
チューリングテストについては、会話ができるというだけで人間の知的能力と同等とみなして良いのか、膨大なデータベースを用意して「カンニング」しているだけでも知性があると言えるのか、など様々な批判や論点があり、実用的なテストとして実施されているわけではない。
しかし、1966年に心理カウンセリングのような対話を行うチャットボット「ELIZA」が開発され、被験者に実際にやり取りをさせてみたところ、相手がコンピュータであると種明かしをしても人間のカウンセラーであると信じて疑わない被験者がいたことが報告され、チューリングテストのコンセプトの有用性が指摘された。
1990年代からは大学などが主催してチューリングテストのコンテストも開かれており、2014年には人間の審判の3割に機械であると見抜かれず、初めて「合格」と判定されたプログラムが登場した。2020年代にディープラーニングや大規模言語モデル(LLM)が発展すると、AIとのやり取りで相手が人間であると誤解する事例が多数報告されるようになっている。