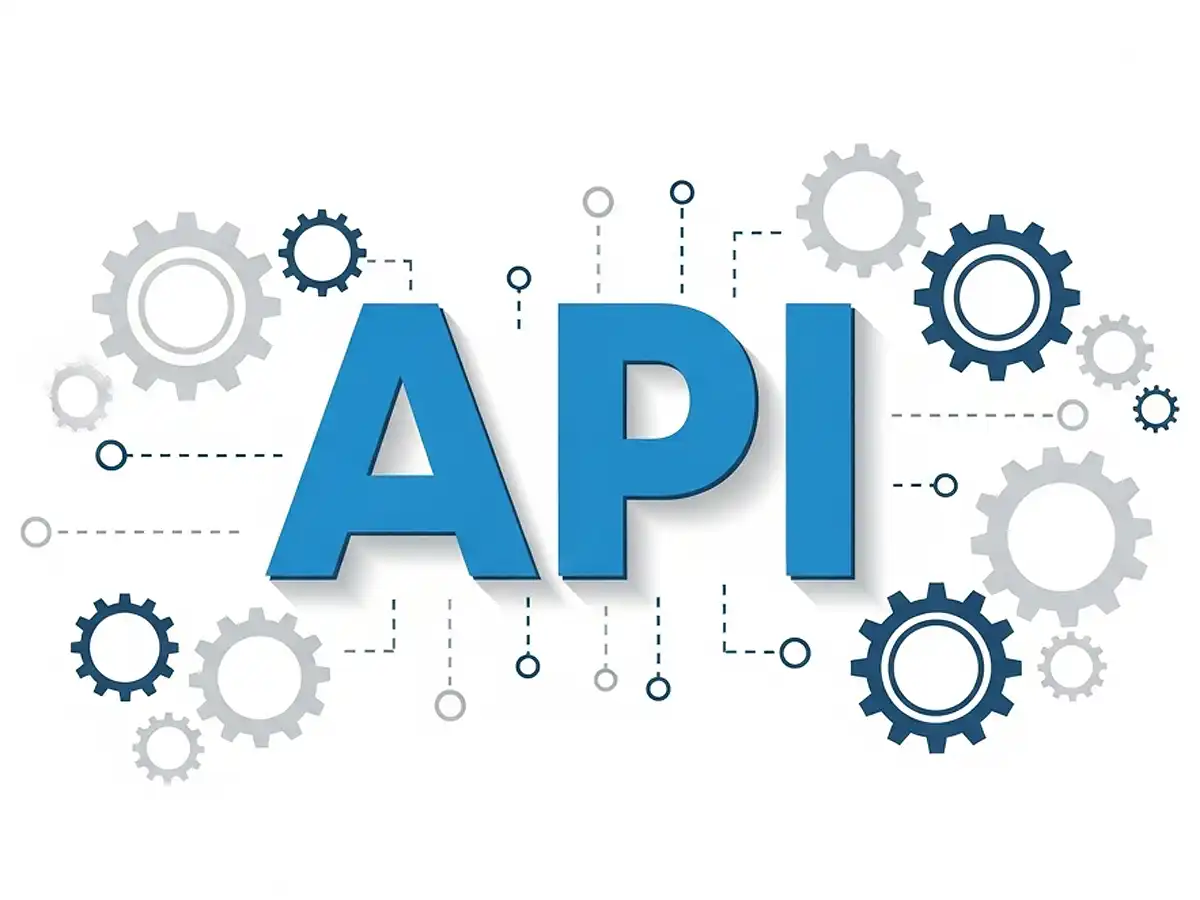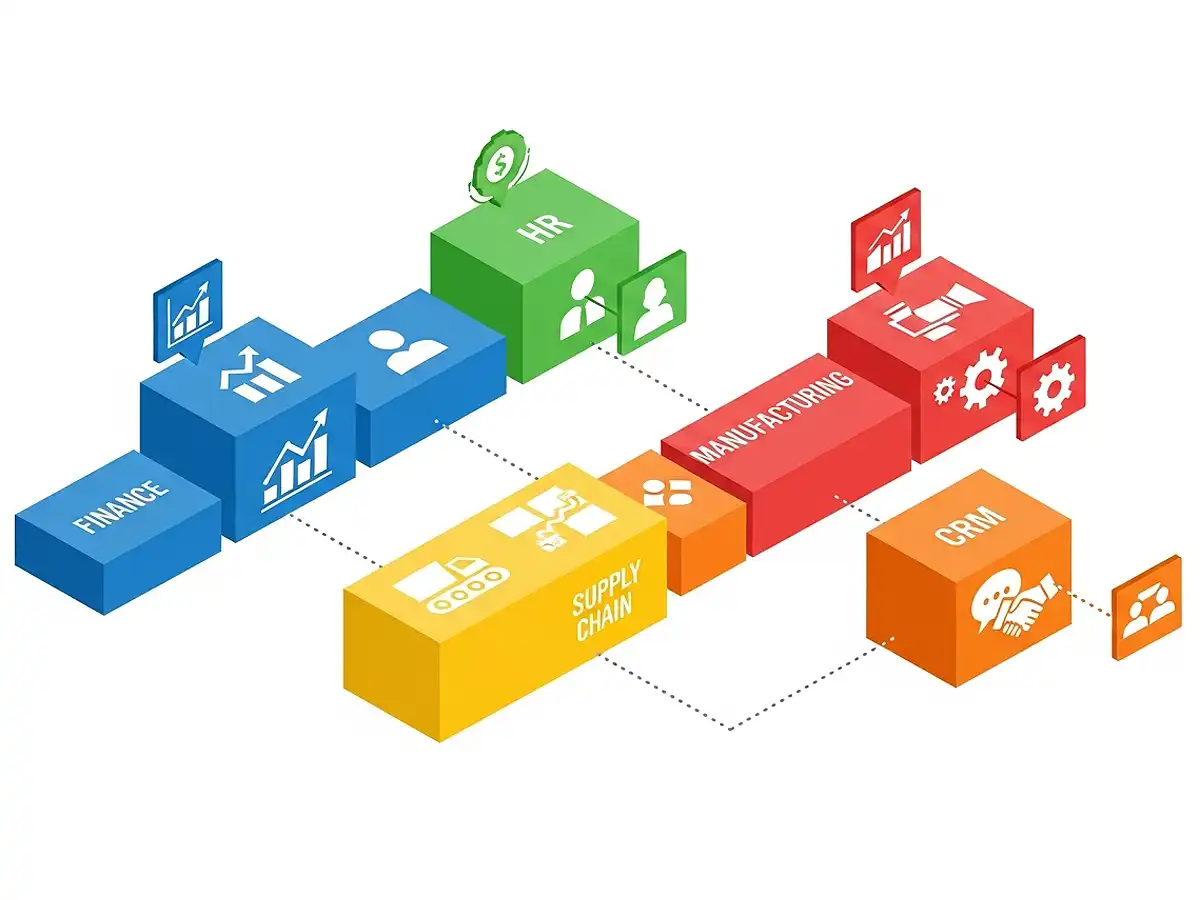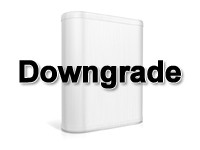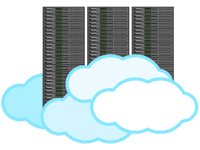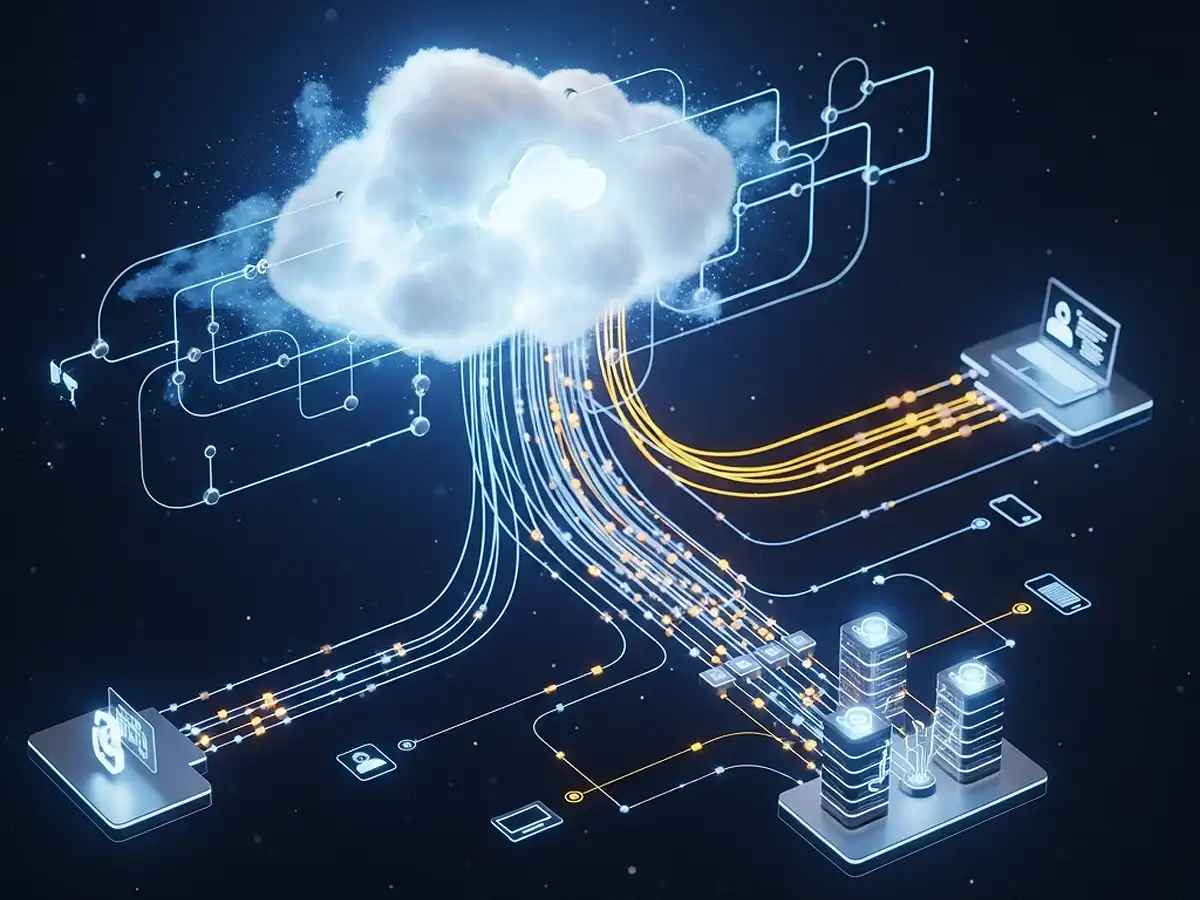SaaS 【Software as a Service】 サービスとしてのソフトウェア
概要
SaaS(Software as a Service)とは、ソフトウェアをインターネットを通じて遠隔から利用者に提供する方式。利用者はWebブラウザなどの汎用クライアントソフトを用いて事業者の運用するサーバへアクセスし、ソフトウェアを操作・使用する。従来「ASPサービス」と呼ばれていたものとほぼ同じもの。解説 従来、ソフトウェアを使用するには利用者がパッケージなどを入手して手元のコンピュータにプログラムを複製、導入し、これを起動して操作する方式が一般的だった。SaaSではソフトウェアの中核部分は事業者の運用するサーバコンピュータ上で実行され、利用者はネットワークを通じてその機能を遠隔から利用する。
利用者側には表示・操作(ユーザーインターフェース)のために最低限必要な機能のみを実装した簡易なクライアントソフトが提供される。専用のクライアントを導入する場合もあるが、一般的には全体をWebアプリケーションとして設計し、利用者はWebブラウザを通じてWebページとして実装されたクライアントを都度ダウンロードして起動する形を取ることが多い。
SaaS方式のソフトウェア提供は2000年代中頃からSFA(営業支援システム)やグループウェアなど業務用ソフトウェアを中心に広まり始め、2010年代以降はERPなどの大規模システム、あるいはオフィスソフト、ゲーム、メッセージソフト(Webメールなど)といった個人向けを含む様々な種類のソフトウェアで一般的になっている。
利用者側から見た特徴
利用者はサービスへ登録・加入するだけで、ソフトウェアの入手や導入を行わなくてもすぐに使い始めることができる。データも原則としてサーバ側に保管されるため、ソフトウェアやデータの入ったコンピュータを持ち歩かなくても、移動先などで普段とは別の端末からログインして前回の作業の続きを行うことができる。
料金もパッケージソフトのように最初に一度だけ所定の金額を支払う「買い切り」型ではなく、契約期間に基づく月額課金や、何らかの使用実績に応じた従量課金が一般的となっている。登録や利用は原則無料で高度な機能や容量などに課金する方式や、広告を表示するなどして完全に無償で提供されるサービスもある。
ただし、利用のためにはインターネット環境が必須で、回線状況によっては操作に対する応答に時間がかかる場合もある。また、サービスを脱退したりサービスが終了してしまうとソフトウェアを使用できなくなり、サーバ側に保存したデータにもアクセスできなくなる。データについては特定の形式でまとめて利用者側にダウンロードできる機能が提供されている場合もある。
事業者側から見た特徴
提供者側から見ると、システムの中核部分はサーバ側で実行され、Webブラウザなどをクライアントとするため、機種やオペレーティングシステム(OS)ごとに個別にソフトウェアを開発・提供する場合に比べ様々な環境に対応しやすい。
また、サーバ側でソフトウェアを常に最新の状態に保つことができ、機能追加や不具合の修正などを利用者側へ迅速に反映できる。機能を細かく分けて利用者が自分に必要なものだけを選んで契約するといった柔軟な提供方式にも対応しやすい。
ただし、処理の多くをサーバ側で行う必要があるため、利用者数や利用頻度などに応じてサーバの台数や性能、データ保管容量などを適切に用意し、必要に応じて増強しなければならない。インターネットを通じてサービスを提供するため回線容量なども提供規模に応じて必要で、単にソフトウェアを販売するより事業者側の投資やコストは重くなりがちである。
PaaS/IaaSとの違い
インターネットを通じて様々な資源や機能をサービスとして遠隔の顧客へ提供する事業形態はSaaS以外にも存在し、総称して「XaaS」(X as a Service:サービスとしての○○)と呼ぶ。
このうち、導入・設定済みのOSやサーバソフト、言語処理系など、アプリケーション実行環境一式(プラットフォーム)をサービスとして遠隔から自由に利用できるようにしたものを「PaaS」(Platform as a Service:サービスとしてのプラットフォーム)という。契約者は自由にアプリケーションを導入して利用することができる。
一方、情報システムの稼動に必要な機材や回線などのIT基盤(インフラ)をサービスとして提供するものを「IaaS」(Infrastructure as a Service:サービスとしてのインフラ)という。契約者はOSやソフトウェア実行環境を整備し、アプリケーションを導入して利用する。
これらの基盤的なクラウドサービスはSaaSとは異なりアプリケーションは提供せず、契約者が自ら用意する必要がある。主に企業などの情報システム部門やネットサービス事業者などが自らのアプリケーションの実行環境として使用するために提供される。
SaaSの例
SaaSとして提供されるアプリケーションは多岐に渡り、一般消費者向けから企業などの業務で用いる法人向け、教育機関向けなど様々な種類がある。インターネット利用者に広く使われているサービスとしては、「Gmail」や「Outlook.com」などのWebメールサービス、「OneDrive」「Google Drive」「iCloud」「Box」「Dropbox」などのオンラインストレージがある。
法人の業務でよく用いられるサービスとしては、「Microsoft 365」「Google Workspace」などのオフィスソフト、「Slack」「Microsoft Teams」「Chatwork」「Zoom」「Google Meet」などのビジネスチャットやWeb会議システム、コラボレーションツールがある。